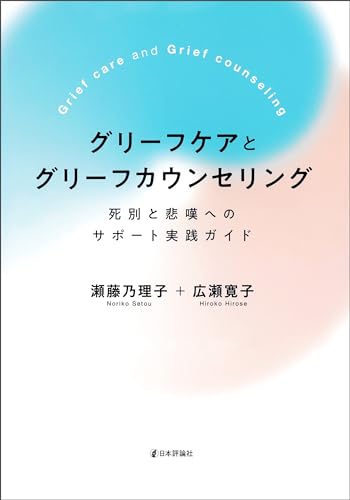------講義録始め------
さて、お気づきの方もおられるでしょうが、ここまで私はグリーフサポートの対象者を喪失体験者と呼んできました。皆さんの中には、なぜ死別体験者ではなく喪失体験者なのだろうと疑問に思った方もおられるかもしれません。
日本ではグリーフを死別悲嘆と訳すこともしばしばあり、グリーフを抱えるのは死別体験者のみであると前提してしまうことが多いように思います。しかし、テキスト第1節第1項で説明したように、グリーフは死別だけでなく、あらゆる喪失体験によって生じ得る反応です。例えば、テキスト第8項「曖昧な喪失とグリーフ」では、行方不明による離別や、コロナ禍で学校に行けない、友達と会えないという機会喪失の体験がグリーフをもたらす例が挙げられています。
死別体験は、こうした多様な喪失体験の1つでしかないのですが、グリーフをもたらす主要な喪失体験であるとは言えるでしょう。ただ、死別体験者という表現は、馴染みのある日本語とは言えません。これは英語で死別で残されたものを意味する「ザ・ビリーブド」(bereaved)という単語の訳語の1つで、他にも死別経験者とか、単に死別者とか、あるいは遺族といった訳語もありますが、今のところ定訳がありません。
死別とは、死によって自分と関わりのある存在を失う経験のことですから、死別喪失の経験者を意味する死別経験者という訳語は適切であると思います。ただ、大切な人と死別した方々から私がお話を伺う中で、自分と同じ状況になってみないとわからない、つまり、大切な人との死別を身をもって経験してみないと理解できるものではないという趣旨の発言を耳にすることがしばしばありました。この死別を身をもって経験するというニュアンスをしっかりと伝えるには、死別体験者の方がより的確かと考えて、個人的には、死別経験者という訳語よりも適していると思います。
なお、グリーフサポートについて書く際には、以前は死別者という表記をしばしば採用していました。この死別者という表記は、人口統計学で配偶者と死別した状態にある夫や妻を指して使われることがあります。ただ、一般の方々に対して死別者という言葉を使った時に、それが死別を体験した当人ではなく、死別させた側を指していると誤解されてしまうことが時々ありました。そのようなわけで、個人的に死別者という表記は現在ほとんど使っていません。
ザ・ビリーブドの訳語として、皆さんにとって最も馴染みのある表現は、やはり遺族でしょう。一般的な用語ですし、医療でもその内容を具体的に知らなくても、遺族ケアという言葉は広く認知されていると思います。本科目でも第10回講義で、グリーフへの専門的対応の1つとして、国内のいくつかの医療機関で開設されている遺族外来を紹介しています。しかし、この遺族という言葉は、ザ・ビリーブドの訳語としては実は適切ではありません。なぜなら、遺族は死別により残された者を親族に限定しているのに対して、ザ・ビリーブドは死別で残された者一般を指す言葉であり、そうした限定をしていないからです。
遺族ケアや遺族外来を字義通り厳密に捉えると、グリーフを抱えてたとえどんなに大きな苦難に直面していても、その人が親族でなければケアや支援を受けられません。ただ、引用文献に挙げた2022年出版の遺族ケアガイドラインでは、遺族ケアを死別に直面した人々への援助や支援と説明しています。また、遺族についても、重要な他者と呼ばれるような人を失った恋人や友人、知人なども深い悲嘆を経験するため、死別を経験するのは遺族だけではないと注意書きが付されています。
ですので、実際には遺族ケアの対象を親族に限定しない柔軟な運営がなされているのかもしれません。とは言っても、法的に認められた親族こそが個人と最も親密な関係にあり、従って死別によるグリーフの影響が最も大きいという前提を、遺族という言葉から拭い去ることは難しいのではないでしょうか。
いずれにしても、グリーフサポートの対象は、遺族に限定されないあらゆる死別体験者ないし喪失体験者であることを、私たちは明確に認識する必要があります。