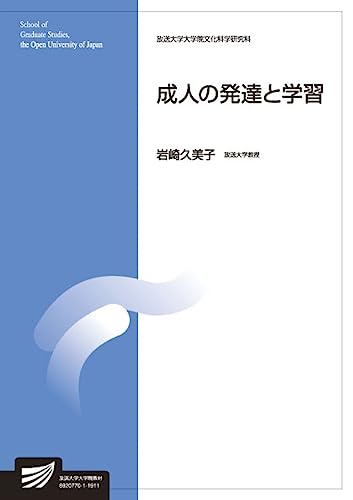ーーーー講義録始めーーーー
堀先生:さて、ノールズの仮説に基づいて、子どもの学習における教授法であるペダゴジーと、成人の学習における教授法であるアンドラゴジーの違いについて具体的に考えてみましょう。
私たちが小学校時代の教室風景を思い浮かべるとわかるように、子どもへの教育は、社会の構成員として自立した大人を育てるために、同年齢集団に対して教師が教科書や教材を用い、標準化されたカリキュラムに基づいて行われます。ここでの学習は、社会による将来への投資と言えるでしょう。
一方、成人の場合は、現実生活の課題や問題に対応するために自発的に学習します。その学習資源は個々の経験であり、それを生かすために討論、問題解決、事例学習、シミュレーション、ワークショップなどが用いられます。子どもと大人の学習は異なり、当然、教授法も異なるものになるということです。ノールズは、このように子どもと大人の学習が異なる点を強調しました。
司会者:ところで、成人教育学をアメリカで広めたノールズに関するエピソードをお話ししたいと思います。堀先生は、ノールズと直接お会いになったことがあると伺いましたが、その時のことを教えていただけますか。
堀先生:はい、よく覚えています。1984年12月に東京大学教育学部でノールズが招聘され、講演会が開かれました。私もその講演会に出席し、そこでノールズに質問しました。私の質問は、「成人教育学と高齢者教育学を分けて考えるべきではないか」というものでした。それに対して、ノールズは少し感情的になりました。
司会者:どうして感情的になったのでしょうか。
堀先生:英語では「高齢者」を"older adults"と言いますが、ノールズは「高齢者もまた成人であり、別に分けるべきではない」と主張したかったのだと思います。高齢者も含めてアンドラゴジーの範疇に入れるべきだという考え方ですね。一方で、ジャック・ルヴェルという人は、「高齢者には高齢者の特有の学習者特性があり、分けるべきだ」と主張し、それを「高齢者教育学(ジェロゴジー)」と呼びました。つまり、教育学はペダゴジー、アンドラゴジー、ジェロゴジーの3つだというわけです。ただし、その内容はまだ完全には整理されていない部分があります。
その後、発達段階理論で有名な心理学者、ロバート・ハヴィガーストに会う機会がありました。
司会者:堀先生は多くの著名な研究者に直接お会いされているのですね。
堀先生:そうですね。当時はこのような研究者を日本に招聘し、講演会を開くことがよくありました。ハヴィガーストに会った際にも、ノールズにしたのと同じ質問をしました。「成人と高齢者を区別するべきではないか」と。
ハヴィガーストは即座に「それは良い考えだ」と賛同してくれました。ハヴィガーストは、発達段階や発達課題を提唱し、人生の各節目ごとに学ぶべき課題があると考えていました。高齢期も明確に区分しており、その考え方に基づけば、成人と高齢者を分けるのは自然なことだというわけです。ノールズは、教育学を過度に細分化することに警戒していたのかもしれませんが、ハヴィガーストは「それでいい」と言ってくれました。